公務員の仕事をしている中で、
「また差し戻し」
「結局、何が言いたいの?」
そんな言葉を投げかけられ、心が折れそうになったことはありませんか?
その原因は能力不足ではなく、単に「考えを論理的に整理し、簡潔に伝える技術」を知らないだけかもしれません。
私自身、長い公務員生活で、説明がうまく伝わらなかったり、何度も資料を作り直したりといった経験をしました。
しかし、「思考の型」と「紙1枚にまとめる技術」を知ってからは、資料作成や説明の場面で迷いがなくなり、どんな相手にも自信をもって話せるようになりました。
この記事では、かつての私と同じ悩みをもつ公務員の方に向けて、「もっと早く知っておきたかった」と心から感じた珠玉の3冊を、実際に読んで実践した経験をもとにご紹介します。
ご紹介する3冊はこちら
| 書籍 | 著者 | 出版社 | ページ数 |
| ロジカルシンキング 論理的な思考と構成のスキル | 照屋華子・岡田恵子 | 東洋経済 新報社 | 227 |
| トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術 | 浅田すぐる | サンマーク出版 | 209 |
| マニャーナの法則 | マーク・フォスター | Discover | 222 |
この記事を書いた人
- 26年間県庁で勤務した元公務員(建築職)
- 総務課(企画)、財政課、住宅政策、耐震、公営住宅などの部署で勤務
- 51歳のときに早期退職し、現在は建築関連の会社に勤務
『ロジカルシンキング 論理的な思考と構成のスキル』(東洋経済新報社)
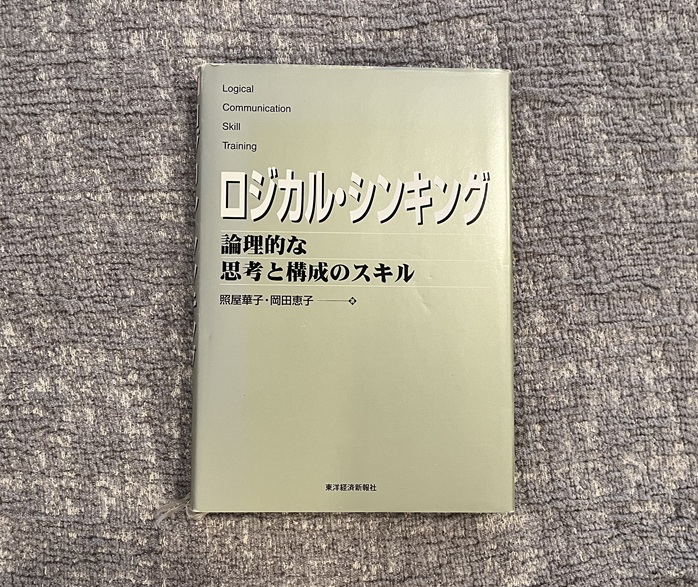
この本の概要
この本は、社会人に必要な「論理的に考え、相手にわかりやすく伝える技術」を実践的に学べる一冊です。
情報の漏れや重複をなくす「MECE(ミッシー)」や、主張と根拠の関係を構造的に整理する「ピラミッド構造」など実務で使える方法がわかりやすく紹介されています。
MECE(ミッシー)とは、ある事柄や概念を、重なりなく、しかも全体として漏れのない部分の集まりで捉えることです。
図や事例を使って丁寧に説明されているので、はじめてロジカルシンキングを学ぶ人にも無理なく理解できます。
『ロジカルシンキング 論理的な思考と構成のスキル』![]() は、論理的な説明が求められる公務員の業務に直結するものなので、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
は、論理的な説明が求められる公務員の業務に直結するものなので、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
私がこの本を読んだ理由
私がこの本を手にしたのは、30代後半の主査のときでした。
企画系の仕事を担当していたため、上司や幹部職員に説明する機会が多かったのですが、「説明がわかりにくい」「何を言っているのかわからない」と指摘されることがたびたびありました。
自分では順序だてて説明しているつもりでも、相手には伝わっていなかったのです。
「なぜ伝わらないのか?」と不思議に思っていたときに、たまたま本屋さんで手にしたのが『ロジカルシンキング 論理的な思考と構成のスキル![]() 』でした。
』でした。
相手にわかりやすく伝えられるよう何度も何度も読み返し、実際の資料作成や説明の場面で実践しながら身につけていきました。
20代のときに読んでいれば、公務員生活が違ったものになっていたかもしれないと思える本です。
読んで印象に残ったポイント
特に印象的だったのが、次の2つの考え方です。
- 思考のヌケモレを防ぐ「MECE」
- 主張に説得力を持たせる「ピラミッド構造」
これらを身につけると、伝えたいことをしっかり整理し、聞いている人にわかりやすく説明できるようになります。
「MECE」で思考がクリアに
この本を読むまで、私が意識していなかったのが、MECE(ミッシー)でした。
話をするときに、漏れやダブりがあると、その時点で論理的な説明にならないのです。
例えば、お肉の話をするときに、牛肉と豚肉の話だけでは漏れがありますよね。鶏肉、ジビエはどうなの?となってしまいます。魚肉は?と思う人もいるかもしれません。
そうなると、牛肉と豚肉についていくら良い話をしても、聞き手は「鶏肉はどうなってるんだ?」となり思考が止まってしまうのですね。
公務員に限らずビジネスの世界では、漏れなくダブりなく説明しなければ、いくら上手に説明したつもりになっていても、理解してもらえることはありません。
「ピラミッド構造」で説得力UP
結論から先に伝え、「なぜそう言えるのか?」を複数の根拠で支えるのがピラミッド構造です。
結論と根拠を階層的に整理することで、主張の全体像が明確になり、聞き手が理解しやすくなります。
例えば、「この制度を導入すべき」という結論に対し、「費用対効果」「他自治体の事例」「市民のニーズ」などの根拠を順序だてて示すことで説得力が高まります。
議会答弁や上司への説明など、論理の一貫性が求められる場面で特に役に立つ考え方です。
こんな人におすすめ!
「話がわかりにくい」「何が言いたいのかわからない」とよく言われる人や、決裁で差戻しが多いと感じている人には特におすすめです。
公務員の仕事では、政策の背景や判断の根拠を明確に説明しなければなりません。感覚的な説明では納得されにくく、下手な説明をすれば県の信頼を損ねることにもつながります。
実際、私がこの本を読んで説得力のある説明ができるようになり、人事評価で「論理的な考え方ができる人物」と言われるまでになりました。
「説明が上手になりたい」と思う人はぜひ読んでみてください。
『トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術」(サンマーク出版)
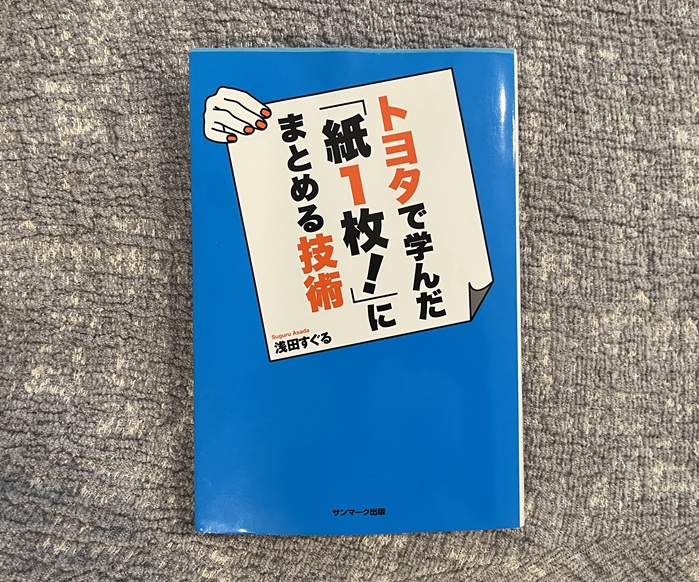
この本の概要
この本は、トヨタの現場で培われた「紙1枚で情報を整理・伝達する」思考整理法を解説した一冊です。
複雑な内容も「一覧性」「フレーム」「テーマ」の3要素で構成された「トヨタの1枚」によって、ひと目で全体像がわかる資料を作ったり、コミュニケーションをスムースに行ったりすることができるというものです。
「紙1枚」に整理するための考え方やフォーマットが、図解とともに紹介されているので、初めての人でも無理なく理解できます。
私がこの本を選んだ理由
私がこの本を読んだのは40歳くらいのときでした。当時、建物の耐震化を担当する部署に配属されていて、幹部職員への「事業説明資料」や「耐震改修促進計画の概要」、「予算要求の概要」といった資料を作る機会が増えていました。
業務量も多く、限られた時間で簡単に作れる方法がないか悩んでいた時に出会ったのが、『トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術』![]() だったのです。
だったのです。
「紙1枚」にまとめる技術で特に効果があった実践ポイント
この本は、幹部職員への説明資料を作成する際にとても役に立ちました。
中でも、「最初の数秒で全体像をつかめる構成」を意識することで、伝わりやすさが格段に向上しました。
幹部職員が一目で理解できる資料を作るコツ
忙しい幹部職員は、資料を隅々まで読みません。
そのため、すべてを読まなくても構成や内容が自然と目に入るように見出しやレイアウトを工夫することが大切です。
と言っても、デザインを凝る必要はありません。「目的」「背景」「対応策」などの見出しを目立つように並べ、それぞれを枠で囲んで整理するだけで、ぐっとわかりやすくなります。
文章をダラダラ書いても読まれないので、箇条書きや体言止めを使って端的な表現を心がけるとさらに伝わりやすくなります。
「紙1枚」に入れておく項目
この本を読むまでは、紙一枚にまとめようとしても何をどう書けばいいかわからず、手が止まることがよくありました。
しかし、この本を読んでからは、以下のような項目を押さえるだけで、ほとんどの内容は整理して説明できることがわかったのです。
- 目的
- 現状
- 課題
- 対策
- スケジュール
- 予算
- 見込める効果
資料の内容によっては、「国の動き」や「他府県の状況」などを加えることで、さらに説得力が上がります。
こんな人におすすめ!
せっかく資料を作っても要点が伝わらなかったり、「何を書いているかわからない」と言われたりすることが多い人には、『トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術』![]() はおすすめです。
はおすすめです。
公務員の世界では、伝える相手が忙しく、資料をじっくり読んでもらえないことがよくあります。
そのため、短時間で本質を理解してもらう工夫が欠かせません。
この本を読めば、「どう見せれば伝わるか」を考えながら資料を作る方法がわかります。
特に、会議資料・幹部職員への説明・議会答弁用の要点整理など、相手に「一目で伝える」機会が多い人におすすめです。
『マニャーナの法則』(ディスカバー)
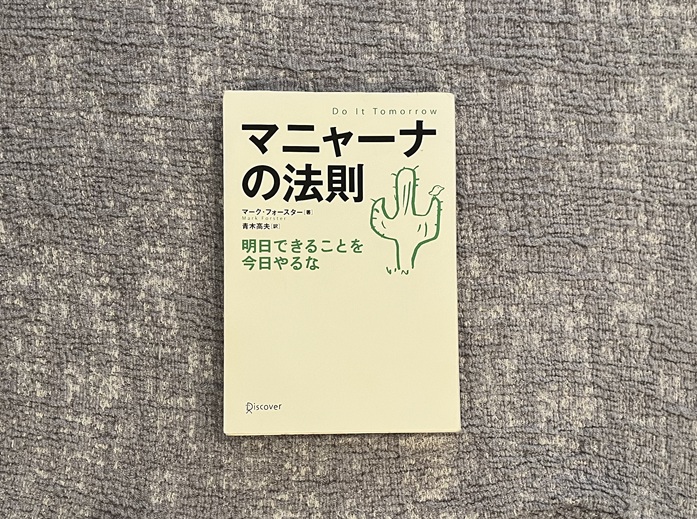
この本の概要
この本は、「今日発生した仕事は、明日やる」という考えをもとにした新しい時間管理術を提案する本です。
これまでにあった「すぐやる」や「優先順位付け」とは異なり、1日のタスクに明確な区切りを設け、仕事を翌日にまとめて処理することで、常に1日分の“バッファー・ゾーン”を確保します。
これにより、心の余裕や集中力が高まり、仕事効率の向上と自己管理を実現できるという内容です。
私がこの本を選んだ理由
私がこの本を読んだのは40歳のとき、建物の耐震化を担当する部署に配属されていたときです。「トヨタの紙1枚」を読んだのと同じ時期ですね。
当時、私の担当業務は「大規模建築物の耐震化促進」で、人員は、課長-課長補佐-主査ー主査(私)だけでした。担当者と呼ばれる若い職員はいません。
業務量が多いわりに職員が少なかったため、とても忙しかったのです。少し話がそれますが、当時の状況は次のような感じでした。
- 緊急案件や新規案件が発生した時には、一番若かった私に仕事が回ってくる。(40歳が一番若いってどうなの?)
- 課長補佐がポンコツな人だったので戦力にならず、課長補佐の仕事もやらないといけない。(部長、課長と一緒に主査の私が、知事レクに出席したこともあります)
- 担当者がいなかったので、「担当者」「主査」「課長補佐」の仕事すべてやっていました。窓口業務、電話応対、議員対応、幹部職員対応、議会答弁作成などです。
残業は月60時間ほどあったので、何とかしてうまく業務をさばきたかったのです。
確か、本屋さんでは売っていなかったので、ネットで取り寄せたように思います。
マニャーナの法則で特に効果のあった考え方
この本で紹介されている時間管理術の中でも、私が特に効果を感じたのは「クローズドリスト」と「ファーストタスク」という考え方です。
どちらもシンプルですが、日々の仕事の質と集中力を大きく変えてくれました。
クローズドリストを使う
クローズドリストとは、その日にやることをあらかじめ決め、それ以上は追加しない仕組みです。
よく使われる「ToDoリスト」は思いついた順に書き足してしまい、タスクがどんどん増えてしまいます。しかし、クローズドリストは「今日やること」に上限を設定するため、やるべきことに集中できます。
私の場合、朝の時点で「今日のタスク」を5件ほどに絞り、それ以外の急な依頼や割り込みは翌日のリストに回しました。
とは言え、緊急案件が入ってくる可能性もあるので、バッファゾーンを設けて急な仕事にも対応できるようにしていました。
この方法に変えてからは、途中で予定が崩れることが減るようになりました。それでも、あふれてしまうくらいの業務量になった場合は、自分のキャパを超えていると考え、ポンコツな課長補佐を飛ばして、課長へ業務改善を直談判していました。
本当に大事な仕事はファーストタスクに
ファーストタスクとは、一日の最初に着手する「最も重要な仕事」のことです。
メールチェックや細かい事務作業よりも先に着手することで、重要業務が確実に前進します。
私の場合、幹部職員への説明資料や議員へ提出する資料の作成など、頭を使う仕事をファーストタスクに設定し、朝一番から取りかかるようにしました。
午前中のうちに大きな仕事を片づけておくと、その後の緊急案件にも余裕をもって対応できます。
「後でやろう」と思っていると、いつの間にか割り込みや雑務に押し出されてしまい、ますます時間が無くなる悪循環。
この本を読んでから、その循環を断ち切れるようになりました。
こんな人におすすめ!
毎日忙しく働いているのに、「本当に大事な仕事ができていない」と感じている方に読んでほしい一冊です。
特に、緊急案件や割り込み業務がよく発生する部署にいて、「やりたい仕事」よりも「やらざるを得ない仕事」に時間を奪われがちな方に向いています。
「重要な仕事を先に進めるための時間の作り方」を知りたい人や、日々の予定をコントロールして前向きに働きたい方には特におすすめです。
私が読んだ本(2007年版)の大幅な改訂版がこちら![]() です。
です。
まとめ
ご紹介した3冊は、忙しい公務員でもすぐに実践できる「仕事効率化の三種の神器」です。
- MECEをベースに、結論と根拠で整理するロジカルシンキング
- 紙1枚で伝える技術
- 朝イチのファーストタスク
どれもシンプルですが、続けるほどに心と時間に余裕が生まれます。
今の働き方に少しでも息苦しさを感じているなら、まずは1冊手に取ってみてください。
公務員生活が大きく変わるかもしれません!
