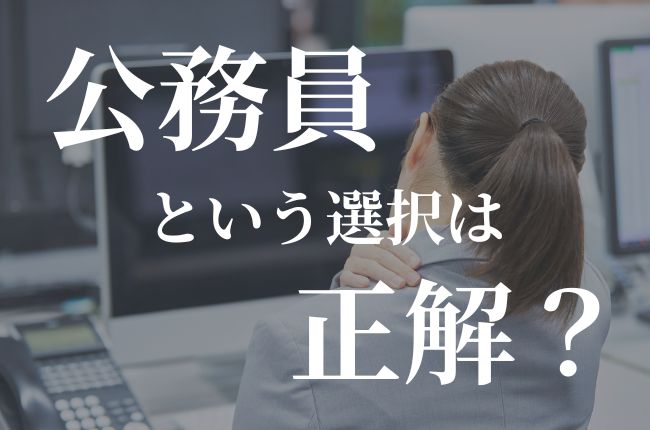「公務員を目指すべきか、それとも他の選択肢を考えるべきか」
「公務員になって後悔することってあるのかな?」
そんな風に悩んだり疑問に思ったりしていませんか。
私は51歳で県庁を早期退職しました。
辞めて2年が経ち、ふと、「 もし、学生に戻ってもう一度就職先を選ぶとしたら、公務員になるのかな?」と考えてみました。
私は公務員にならないでしょう。
私がなぜそう考えるのか、具体的な理由と退職後の生活について、お伝えしたいと思います。
この記事を書いた人
- 26年間県庁に勤め、51歳で早期退職した元公務員(建築職)
- 在職中は、総務課・財政課・耐震・住宅政策・公営住宅などの部署を経験
- 現在は、建築関連の民間企業に勤務
- 保有資格は、一級建築士、宅地建物取引士、FP2級
就職先として「公務員を選ばない」と考える5つの理由

もう一度学生に戻ったとしても、就職先として公務員を選ばない理由は以下のとおりです。
- 市場価値を高めるスキルが身につかない
- 給料が安い(民間の同期と比べると唖然)
- 「ワークライフバランス神話」の崩壊と働き方の変化
- 頑張っている人が評価されない
- 失敗を認めない独特の世界
市場価値を高めるスキルが身につかない
公務員の仕事では、転職市場で評価されるような専門スキルは身につきにくいです。
入庁した時に、上司から言われた「公務員にスペシャリストはいらない。優秀なゼネラリストになれ」と言う言葉が今でも印象に残っています。
スペシャリストとは、特定の分野に深い知識や技術を持つ専門家のこと。
ゼネラリストとは、ゼネラリストは幅広い分野の知識や経験を持つ人材のこと。
公務員組織は、後者のゼネラリストを育成する方針を採っています。
私は建築職として入庁しましたが、建築の設計や工事監理を直接担当する機会はほとんどありませんでした。
自分で設計して積算し、工事監理したのは3年だけです。実は3年でも長いほうかもしれません。
というのも、設計や工事監理は設計事務所へ委託するのが一般的だからです。
私が担当した主な業務は、職種に関わらず多くの公務員が経験する以下のような内容でした。
- 住民へのお知らせ文書や市町村への照会文書の作成
- 補助金の算定業務
- 関係部署との調整(仕事の押し付け合いも含む)
- 幹部職員や議員への説明資料の作成と説明
- 議会答弁案の作成・幹部職員へのレク
- 関係団体の応接
これらは「調整能力」や「プレゼン能力」とはいえますが、建築職としての専門性が高まる業務ではありません。
数年ごとの人事異動でいろいろな業務を経験する公務員は、組織内では重宝されるかもしれませんが、市場価値の高いスキルを習得するのはむずかしい状況です。
給料が安い(民間の同期と比べると唖然)
公務員の給料は、民間企業と比べると低い水準です。
安定した職業と言うイメージがありますが、特に若手のころは給料が少ないと感じたものです。
福利厚生が手厚いので、ある程度は仕方ないと僕は考えるようにしていました。
どれくらい少ないかと言うと…。
僕の最高月収は、大学卒業後に入社した民間企業で記録したものです。
当時23歳で連日深夜まで働き、残業代をすべて申請した結果、手取り額は基本給の3倍弱でした。
公務員として働いていたときでも、この月収を超えたときはありません。
民間に就職した大学の同期と給料の話をした時には、その差に愕然としたことを覚えています。給料もボーナスも完敗でした。
公務員の給料は、仕事ができるできないに関わらず、ほぼ年齢で決まります。
そのため、まじめに熱心に仕事をしても給料に反映されにくく、納得できないと感じる職員もいます。
給料が安いのはわかっていたけど、これだけ少ないとは!と思っている人も多いはずです。
「ワークライフバランス神話」の崩壊と働き方の変化
かつて公務員の魅力だったワークライフバランスは、今では必ずしも保証されていません。
約30年前、僕は民間企業で深夜まで働く毎日に疑問を感じ、「自分の時間が欲しい。人間らしい生活をしたい」と思い公務員へ転職しました。
当時は、今ほど働き方の選択肢がなく、その決断にはとても満足していました。
実際、30代までは仕事と私生活のバランスがとれていて、理想的な働き方ができていたのです。
しかし、40代以降、状況は一変します。
議会や幹部職員、マスコミへの対応が主な業務となり、常に相手の都合が優先されました。自分の時間を確保することは難しくなり、働きづらさを感じる場面が増えていったのです。年休を予定していても、急遽出勤せざるを得ない状況も数えきれないほど経験しました。
残業時間は配属された部署に大きく左右され、例えば、財政課にいた時は、予算要求時期の11月から2月の4ヶ月で500時間に達しました。年間トータルではさらに増えます。
時代は変わり、今では民間企業のほうがリモートワークやフレックスタイムが導入され、柔軟な働き方ができる場合があります。30年前では考えられなかったフリーランスという選択肢もありますね。
さらに、公務員特有の根本的な問題もあります。人員が不足しているからと言って事業を中止する判断はできません。また、知事や部長、課長が代わるたびに新しい事業が始まり、業務量は増え続けます。人は減るのに仕事が増える典型ですね。
対照的に、僕が今働いている会社では、社員が抱えきれないほどの仕事は受注しません。協力会社との連携や、時には丁重にお断りして業務量を適切に管理しています。
昔と違って働きやすさの観点では、公務員が最適だと言えない時代になったと感じます。
頑張っている人が評価されない
公務員の人事評価は、必ずしも仕事の成果と連動しません。
評価基準はあるものの、基準そのものがあいまいで、上司の主観や人間関係に左右される場合があるからです。
上司が部下の業務内容を正確に把握していなかったり、評価する能力がなかったりするケースもあります。
その結果、業務成果と関係のない要素が評価に影響を与えてしまう不公平感がありました。
- 声の大きさや発言力
- 上司との人間関係の良し悪し
- 熱心に働いている雰囲気の演出
といったものですね。
僕が課長補佐として人事評価の一次評価を担当した時、この問題を実感する出来事を紹介します。
異動した先の部署に、ある主査と関係が良くないという理由で、前年度の評価が低い若手職員がいました。
しかし、実際に一緒に働いてみると、その職員の能力は高く、自分の意見をしっかりもちながらも協調性があり、常にチームのことを考えて仕事をします。急な仕事でも責任をもって最後までやり遂げ、上司や住民への対応も丁寧。温和な性格でトラブルを起こすような人ではありません。
前年度の評価に疑問を感じた僕は、彼の実績を正当に評価し、グループ内で最高クラスの評価をつけました。
すると案の定、課長から「なぜ彼の評価がこんなに高いのか」と聞かれます。僕はその職員の能力や仕事への姿勢を具体的に説明し、「前年度の評価がおかしい」と伝えました。おそらく、関係の悪い主査から前任の課長補佐へ偏った情報が伝わり、それを基に評価されていたのでしょう。
また、人事評価制度そのものが形骸化している面もあります。
「S・A・B・C」の4段階評価があっても、大半の職員は「B(普通)」に落ち着き、実質的な差がつかない「評価のための評価」になっています。昇進を控えた職員に、後付けの理由として「S(優秀)」をつけるようなケースも見てきました。
実際、「なぜあの人が出世するの?」という疑問はよくあることです。
仕事をすべて部下に任せきりにする上司や、何も自分で決められない課長、そんな人に限ってなぜか出世する不思議な世界でした。
失敗を認めない独特の世界
公務員の世界では、失敗そのものを認めない独特の文化があります。
民間企業では、失敗を分析し改善して次に活かすことが一般的ですが、公務員では同じようにはいきません。
行政計画がうまくいかなかった場合などでも、それを「失敗」とは認めません。
「想定できなかった事態が生じた」「相手方の事情があった」など、失敗ではなく「仕方がない」と言うための理由を探し出すのです。
若手のうちは純粋に業務に集中できますが、40代を過ぎると、こうした「失敗ではない理由を探す」ための調整や資料作成が仕事の大半を占めるようになります。
「失敗の先に成功がある」という考え方を持つ人には公務員は向いていないでしょう。
僕の経歴

僕の経歴を簡単にご紹介します。
【20代〜30代】専門性を活かせた充実期
大学で建築を学び、民間企業で2年間、震災復興事業に携わったあと、建築職として県庁に入庁しました。
入庁後の数年間は、公共建築物の設計や工事監理など専門性を活かせる業務が多く、充実していました。CADを使って発注図面を作り、実際に工事監理していたのはこのころです。外郭団体への出向も経験し、やりがいを感じていた時期でした。
【40代】歯車が狂いはじめた転換期
40代で、まったく興味のない総務課へ異動したころから、少しずつ歯車が狂いはじめます。「建築の仕事がしたい」という思いとは裏腹に、内部調整に追われる日々が増えていきました。
40代半ばで、激務で知られる財政課に行った経験は、心身ともに厳しいものでした。財政課のことはこちらの記事で書いていますので、見てみてください。
また、40代後半で、実態にそぐわない行政計画の後処理を任されたときは、理不尽さを強く感じました。計画を策定した時の職員は責任を問われず、後の担当者が尻拭いをする現実に、やりきれない思いが募ります。このころから、退職を具体的に考えはじめました。
【50代】退職の引き金となった組織改悪
そして退職の直接の引き金になったのが、50代で経験した組織改編です。仕事量は変わらないのに、2つのグループが1つに統合され、そのグループ長になったときです。これは現場の実態を無視した数合わせに過ぎず、モチベーションは下がる一方でした。こなせるはずのない膨大な業務量で、「このままでは潰されてしまう」と感じ、実際にストレスから健康を害したのをきっかけに、退職を決めました。
もちろん公務員にもメリットはある

ここまで公務員の厳しい面について書いてきましたが、もちろん良い点もあります。僕が在職中に感じたメリットを3つ紹介します。
- 社会貢献を直接実感できる
- 安定した収入と手厚い福利厚生
- 社会的信用の高さ
社会貢献を直接実感できる
公務員の仕事には、社会貢献を直接実感できるという大きなやりがいがあります。
たとえば、僕が所属していた耐震化を促進する部署では、大地震が起こった時に、入居者や施設利用者の安全性を確保するため、建物所有者の負担が軽くなるよう耐震化補助金を創設しました。社会全体の安全性を高めるという観点で、大きな意味があったと考えています。
また、公営住宅を管理する部署では、入居者が暮らしやすくなるようバリアフリー工事なども行いました。住民の安全性向上と快適な生活空間の実現に関わる仕事だと思います。
自分の仕事が社会基盤を支え、人々の安全な暮らしに貢献していると感じられる点は、公務員ならではの魅力といえるでしょう。
安定した収入と手厚い福利厚生
安定した収入と手厚い福利厚生は、公務員の大きな魅力です。
民間企業のように業績や景気の影響を受けにくく収入が安定しているため、長期的な生活設計を立てやすいですね。
各種手当や休暇制度、共済組合のサービスなども整っているので、安心して働ける環境が用意されています。
社会的信用の高さ
退職して改めて実感するのが、公務員と言う職業の社会的な信用の高さです。
収入が安定し倒産のリスクもないため、特に金融機関からの信頼は厚いものがあります。
僕は、住宅ローンを組む際にそれを強く実感しました。審査が驚くほどスムーズに進み、ローンが組めなくなるかもしれないという心配はしたことがありません。
人生の重要な局面で感じる社会的信用の高さは、公務員ならではのメリットといえるでしょう。
公務員を辞めて2年、現在の生活【後悔なし】

公務員のメリットは十分理解していますが、それでも辞めたことに後悔は一切ありません。
県庁を退職して約1年後、民間企業へ転職し、現在は正社員として働いています。勤務形態は週3日の出勤とリモートワークの組み合わせです。1日5時間勤務で残業はなく、副業に取り組む時間も確保できています。この柔軟な働き方のおかげで、旅行や遠方に住む子供たちに会いに行く予定も立てやすくなりました。
また、精神的なストレスは完全になくなりました。退職する直前は、幹部職員や議員への対応、膨大な業務に追われる日々が続き、ストレスが原因で急性膵炎を患いました。今では完治し健康で穏やかな毎日を過ごしています。
現在の職場は社員20名ほどですが、人間関係は良好です。公務員時代は、どの部署にも必ずと言っていいほど変な人がいましたが、今はそんな人に振り回されることはありません。
将来的にはフリーランスとして、さらに自由な働き方を模索するのも良いかなと考えています。
公務員を辞めた決断は、心の底から正しかったと感じます。
まとめ
公務員を辞めて2年が経ち、ふと「学生に戻ったら、もう一度公務員を目指すかな?」と考えたことから、この記事を書きました。
公務員の仕事には魅力ややりがいもありましたが、建築の勉強をしてきた者としては、住宅や建築の実務をもっと経験したかったという思いもあります。
それでも、公務員として得た多くの経験や、出会えた人たちには心から感謝しています。
この記事が、これから公務員を目指す方や、現在の働き方に悩んでいる方にとって、ご自身のキャリアを考えるうえでの一助となれば幸いです。
今後は、これまでの経験を活かしつつ、組織に縛られない自由な働き方で、新たな挑戦を楽しんでいきたいと思います。